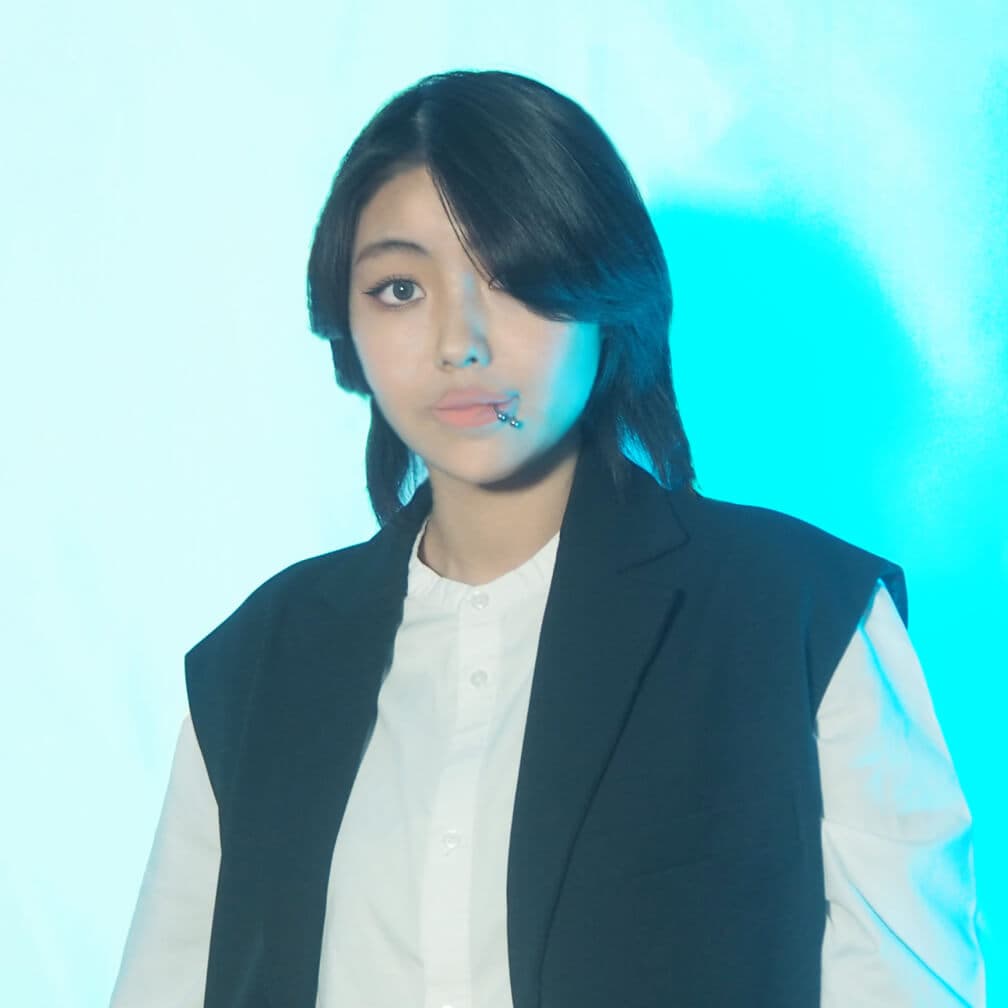デザイン思考を持った課題解決の進め方のコツ
デザイン思考を持った課題解決の進め方のコツ
こんにちは!
今回は「デザイン思考を持った課題解決の進め方のコツ」というテーマで進めていきます。
デザイン思考は様々なフレームワークで表現されますが、基本的には利用者を中心として課題解決策を行うことが重要視されています。デザイン思考を持ったデザイン制作や企画制作などを行なったとしても、利用者にそのデザインが響かないと意味がありません。
そのため、今回は結果に響かないような失敗がないように課題解決の進め方のコツを3つ紹介するので、最後まで是非ご覧ください!
- 目次
- 1.利用者中心に考える
- 2-1 作りながら考える
- 2-2 事業プロセスごとの自由度と資源配分を知る
- まとめ
1.利用者中心に考える
デザイン思考では利用者中心にし、課題の定義や解決策を練っていくことを重視しています。
現代において人々に受け入れられるサービスを開発するには、
オンライン、オフラインなど複雑化した利用者を取り巻く状況を理解する
↓
多様化する利用者の価値観を捉える
↓
求められているニーズを把握し、新しいサービスを考える
このように独自の価値を提案していくことが求められています。
利用者のことを広く深く見ていく必要があります。

複雑化した利用者を見ていくことはとても大変なことです。
なので少しでも複雑化したものをわかりやすいようにするために情報を視覚化する必要があります。
オススメの視覚化の方法を2つ紹介します!
◎カスタマージャーニーマップ
.png)
これは行動、サービスの接点、行動ごとの感情などを時系列に表していきます。
利用者がサービスを利用する複雑な状況を視覚的に捉えることで、課題や解決策を見つけやすくなり、
共通認識を仲間同士で持つこともできるためオススメです。
◎KA法

利用者にインタビューをして心の声や行動の情報を集めて分析することで、利用者の潜在ニーズを導き出すことができます。
2-1 作りながら考える
作りながら進めることの最大のメリットは失敗の可能性を下げられることです。
サービスを具体的に作る前に利用者からのフィードバックを得ることで思い込みや見落としを防ぐことができ、的外れなサービスを作ってしまうというような可能性を下げることができます。
2-2 事業プロセスごとの自由度と資源配分を知る

上記の表を見て分かるようにプロセスの後半に行くほど自由度が下がり、資源配分は上がります。
実行に近づくにつれて、資源配分(人・もの・お金・時間)が上がるため変更の自由度が下がってしまうため、プロセスの前半から利用者からのフィードバックや繰り返しシミュレーションを行うことが重要になります。
まとめ
今回の内容は以上になります!いかがでしたか?
現代の複雑化した課題解決を見つけ出すのはとても難しいことですよね。
視覚化することで仲間同士の共通認識や企画の進め具合など少しは変わってくるかと思います。
1つの方法として取り入れてみてはいかがでしょうか?
次回またお会いしましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました。