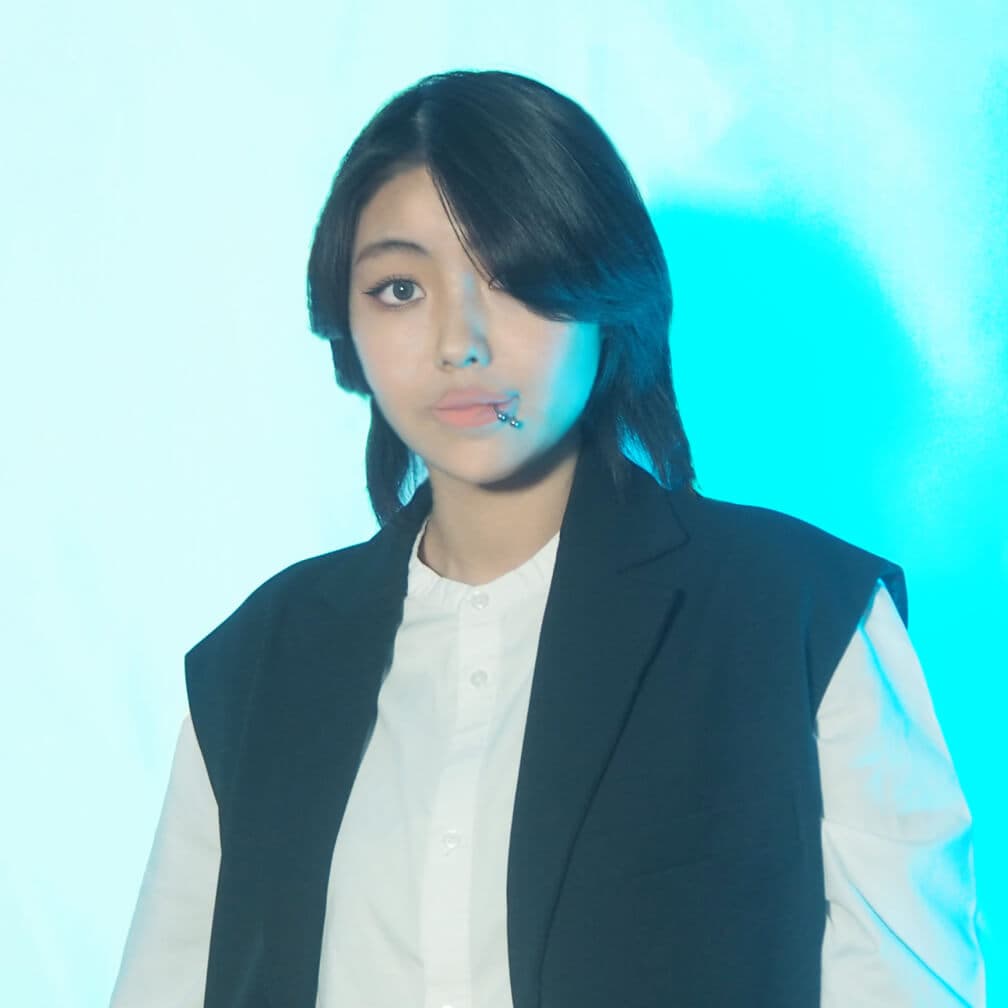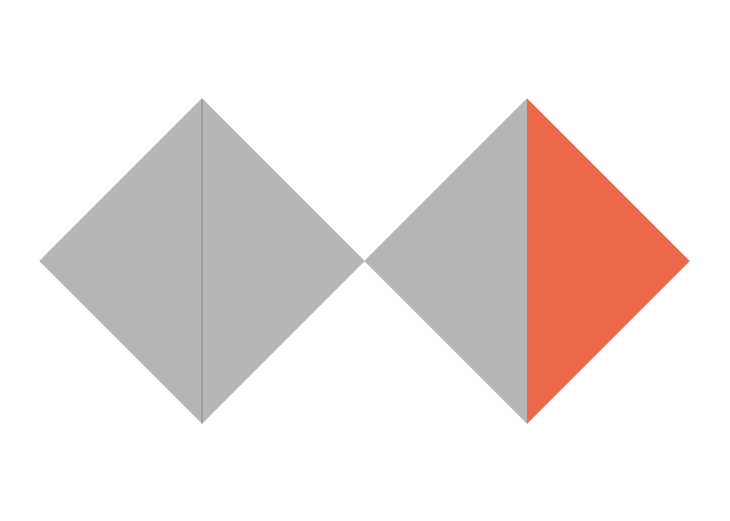
「実現」ステップの中身
「実現」ステップの中身
こんにちは!
今回はダブルダイヤモンドの最後のステップ4「実現」について進めていきます。
「実現」の目的
名前の通りサービスの実現を目指します!
「サービスが実際に利用者に価値を提供できるという確信を持つ」
「サービスがマーケットに対して独自の価値提供ができているという確信を持つ」
この2つができている状態にしておきます。
最後のステップ「実現」を抑えてダブルダイヤモンドのデザイン思考の流れを一緒に理解しましょう!
目次
- 「展開」ステップとの違い
- 「実現」ステップの進め方
- 「実現」ステップの考え方
- まとめ
・「展開」ステップとの違い
ここで簡単に「展開」ステップとの違いを説明します。
展開ステップでは、定義ステップで出た問いに対して解決の可能性を幅広く検討するために、
抽象的なアイディアを具体化するプロトタイピングを行っていました。
実現ステップでは、幅広く検討した解決策を実際に試して改善し、解決策を絞り込むために、
プロトタイピングを行います。
拡散するためのプロトタイピング→展開ステップ

収束するためのプロトタイピング→実現ステップ

そんなに違いがないように見えてしまうかもしれませんが、実現ステップはサービスの実現に向けて改善を繰り返すため長い時間がかかる可能性があります。
・「実現」ステップの進め方
実現に向けて段階的にプロトタイプを作成しますが、完璧に作る必要はありません。
必要最低限の条件が揃っていれば大丈夫です。
そのような方法をMVP(Minimum Viable Product)と言います。
例題:移動をサポートする価値を実現するための商品を作る

上記のイラストのように、移動するために車の一部である車輪だけを作っても意味ありません。
なので、車を時間とコストをたくさんかけて作りました。ですが失敗した場合どうなるでしょうか?
失敗に終わった車は時間とコストを無駄にしてしまいますよね。
そうならないために、まずはスケートボードやキックスケーターなどといった移動に必要な最低限の機能が付いたものを使って、利用者の反応を見て、段階的にアップデートをしていくという考え方です。
MVPの考え方を使えば仮に失敗に終わったとしても、すぐに修正が可能であるため
時間とコストを最小限に抑えて次に進むことができます!
・「実現」ステップの考え方
思考モードは全体的に使います。下記のイラストのように思考モードをぐるぐる回るような感じです。

1.具体制作モード
→プロトタイプの制作を行う
2.事実確認モード
→開発したプロダクトをもとに利用者に対してインタビューなどを行い、フィードバックを得る
3.本質分析モード
→得られた情報を整理、分析して重要となるポイントを捉える
4.方針探索モード
→次に何をすべきかの筋道を立てる
5.具体制作モード
→新しいバージョンのプロトタイプを作成する
どの思考モードでも客観的な視点を持つこと受け入れることが大切です!
そして、このようなに繰り返し続けてサービスの実現を目指していきます。
・まとめ
今回の内容はこちらで以上になります。いかがでしたか?
ここまで4つの中身を紹介してきましたが、デザイン思考という考え方を少しでも理解していただけたら嬉しく思います。商品やサービスを生み出す方法というのは世の中にたくさんあります。
また状況や目的、メンバーなどによって本当に大きく変わってくると思います。
ですので、一つの方法として理解していただければと思います!
また次回お会いしましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました。